| Manholeの旅トップページ | 天竺老人トップページ |
| Manholeの旅 沖縄県 |
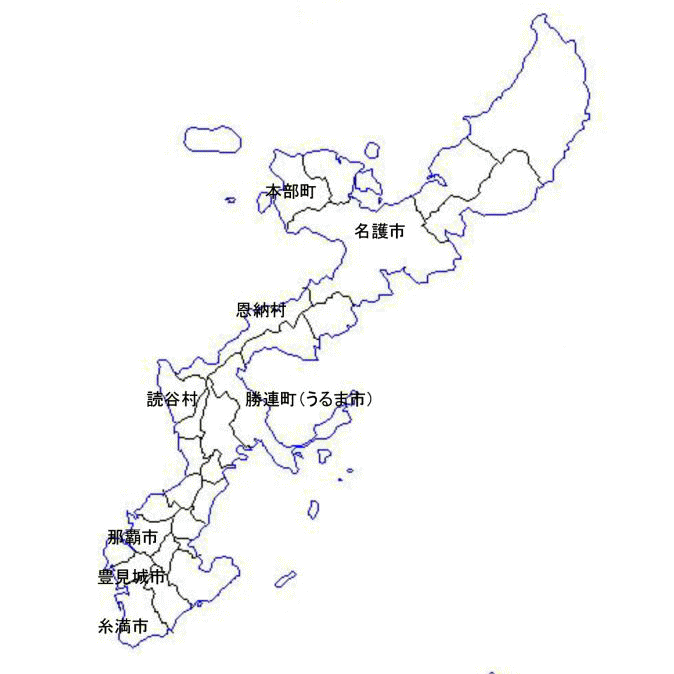 |
本部町 |
| 名護市 | |
| 恩納村 | |
| 読谷村 | |
| 勝連町 | |
| 那覇市 | |
| 豊見城市 | |
| 糸満市 | |
 |
本部町(もとぶちょう)  沖縄北西部、本部半島の先端に位置する町。昭和50年に開催された沖縄国際海洋博覧会の会場となり、美ら海水族館は現在でも多くの観光客を集めている。町の木は「フクギ」町の花は「らん」「さくら」町の鳥は「リュウキュウコノハズク」町の魚は「カツオ」町の蝶は「コノハチョウ」マンホールの蓋にはこれらシンボルが描かれている (2012.03.04撮影) 沖縄北西部、本部半島の先端に位置する町。昭和50年に開催された沖縄国際海洋博覧会の会場となり、美ら海水族館は現在でも多くの観光客を集めている。町の木は「フクギ」町の花は「らん」「さくら」町の鳥は「リュウキュウコノハズク」町の魚は「カツオ」町の蝶は「コノハチョウ」マンホールの蓋にはこれらシンボルが描かれている (2012.03.04撮影) |
|||
 |
||||
 |
||||
 |
名護市  名護市は沖縄本島の北部に位置し、この地域の中心都市。薩摩の支配時代に米作の基盤が整備され、昭和になってサトウキビの栽培が盛んになる。中世より「ウコン」が特産物として有名。マンホールの蓋には町の花「カンヒザクラ」と「テッポウユリ」、町の鳥「リュウキュウメジロ」が描かれている。(2012.03.05撮影) 名護市は沖縄本島の北部に位置し、この地域の中心都市。薩摩の支配時代に米作の基盤が整備され、昭和になってサトウキビの栽培が盛んになる。中世より「ウコン」が特産物として有名。マンホールの蓋には町の花「カンヒザクラ」と「テッポウユリ」、町の鳥「リュウキュウメジロ」が描かれている。(2012.03.05撮影) |
|||
 |
||||
 |
恩納村(おんなそん)  沖縄本島の中央部西海岸に面した村。半農半漁の静かな村であったが、国際海洋博覧会以降にリゾート地として脚光を浴び、大型観光施設が林立するようになった。村の花は黄色い花の「ユウナ」村の木は「フクギ」マンホールの蓋にはサンゴ礁の海に浮かぶヨットと町のシンボルが描かれている。(2012.03.04撮影) 沖縄本島の中央部西海岸に面した村。半農半漁の静かな村であったが、国際海洋博覧会以降にリゾート地として脚光を浴び、大型観光施設が林立するようになった。村の花は黄色い花の「ユウナ」村の木は「フクギ」マンホールの蓋にはサンゴ礁の海に浮かぶヨットと町のシンボルが描かれている。(2012.03.04撮影) |
|||
 |
||||
 |
読谷村(よみたんそん)  沖縄本島中部の西海岸、残波岬のある半島に位置する村。琉球から明への初めての朝貢船に読谷村の”泰期”が使わされた歴史を持つ。村の花は「ブーゲンビレア」村の木は「フクギ」マンホールの蓋は「座喜味城跡」付近で写したもの。朝貢船と村章が描かれている。(2012.03.05撮影) 沖縄本島中部の西海岸、残波岬のある半島に位置する村。琉球から明への初めての朝貢船に読谷村の”泰期”が使わされた歴史を持つ。村の花は「ブーゲンビレア」村の木は「フクギ」マンホールの蓋は「座喜味城跡」付近で写したもの。朝貢船と村章が描かれている。(2012.03.05撮影) |
|||
 |
||||
 |
勝連町(うるま市)  勝連町(かつれんちょう)は沖縄本島中部東海岸に突き出た勝連半島に位置した町だったが、2005年4月に周辺4市町が合併して「うるま市」となる。エイサー踊りが描かれているマンホールの蓋は世界遺産に登録されている勝連城跡付近で写したもの。シンボルマークはうるま市の市章。 (2012.03.06撮影) 勝連町(かつれんちょう)は沖縄本島中部東海岸に突き出た勝連半島に位置した町だったが、2005年4月に周辺4市町が合併して「うるま市」となる。エイサー踊りが描かれているマンホールの蓋は世界遺産に登録されている勝連城跡付近で写したもの。シンボルマークはうるま市の市章。 (2012.03.06撮影) |
|||
 |
||||
 |
那覇市  琉球王朝の中心都市。「ナハ」は「ナバ(漁場)」から発生した呼び名との説もあり、古くは「ナーファ」または「ナファ」とも呼ばれた。市の花は「ブーゲンビレア」市の木は「フクギ」市の花木は「ホウオウボク」市の魚は「マグロ」。マンホールの蓋の図柄は市章を中心に口を開けた魚(多分マグロ)が取り囲んでいる。(2012.03.06撮影) 琉球王朝の中心都市。「ナハ」は「ナバ(漁場)」から発生した呼び名との説もあり、古くは「ナーファ」または「ナファ」とも呼ばれた。市の花は「ブーゲンビレア」市の木は「フクギ」市の花木は「ホウオウボク」市の魚は「マグロ」。マンホールの蓋の図柄は市章を中心に口を開けた魚(多分マグロ)が取り囲んでいる。(2012.03.06撮影) |
|||
 |
||||
 |
豊見城市(とみぐすくし) 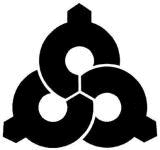 沖縄本島南部の西海岸に位置。農業と漁業の町であったが那覇市に隣接していることから近年は同市のベットタウンとして人口が急増した。市の花は「ブーゲンビレア」市の木は「リュウキュウコクタン」マンホールの蓋の中心には「と」を三つ重ねて、円形は城(ぐすく)を表している市章が描かれている。(2012.03.06撮影) 沖縄本島南部の西海岸に位置。農業と漁業の町であったが那覇市に隣接していることから近年は同市のベットタウンとして人口が急増した。市の花は「ブーゲンビレア」市の木は「リュウキュウコクタン」マンホールの蓋の中心には「と」を三つ重ねて、円形は城(ぐすく)を表している市章が描かれている。(2012.03.06撮影) |
|||
 |
||||
 |
糸満市  沖縄本島の最南端に位置。漁業の盛んな市で「海人(ウミンチュ)」の町として有名。摩文仁の丘からは珊瑚礁の広がる美しい海が眺められる。市の花は「日日草」市の花木は「ブーゲンビレア」市の木は「ガジュマル」市の魚はフエキダイ科の「タマン」マンホールの蓋の中心には市章が描かれている。(2012.03.06撮影) 沖縄本島の最南端に位置。漁業の盛んな市で「海人(ウミンチュ)」の町として有名。摩文仁の丘からは珊瑚礁の広がる美しい海が眺められる。市の花は「日日草」市の花木は「ブーゲンビレア」市の木は「ガジュマル」市の魚はフエキダイ科の「タマン」マンホールの蓋の中心には市章が描かれている。(2012.03.06撮影) |
|||
 |
||||
| ページトップ |
| Copyright(C)tenjikuroujin.jp All rights Reserved |