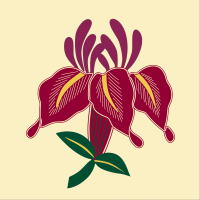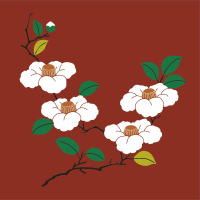雪ちるや おどけも言えぬ 信濃空(しなのぞら) 雪ちるや おどけも言えぬ 信濃空(しなのぞら)
小林一茶 文政2年(1819)
1月6日は二十四節季のうち「小寒(しょうかん)」。冬の寒さが最も強まるころ。これから2月3日の節分迄を「寒の内」あるいは「寒中」と言っている。暦の上ではもっとも寒さが厳しい時期というが、小寒の日の今日の横浜地方は最低気温は4.5度であったが、最高気温は17.5度まで上がる予報。
一茶の句は旧暦の12月の作。太陽暦であれば1月から2月ころか。一茶が終の棲家と定めた生まれ故郷の信濃の柏原は豪雪地帯。「はつ雪や といえば直ぐに 三、四尺」の句も残している。
雪が珍しい都会に住む者にとって一面真っ白に覆われた神秘的で美しい雪景色を待ち望んでいる者も多いが、一茶にとっては雪の降るのを待ち焦がれるとは冗談やたわむれ(おどけ)にも言えない言葉。冬の到来は4,5ヶ月ほど続く戦そのもの。
元日に震度7の地震が襲った能登半島、輪島の今日の最低気温は6.5度。最高気温の予想は12度で天候は雨。一転して明日の最低気温は0.7度、最高気温は2.9度の予報。天候は大雪が予想されている。震災被害を思えば雪景色を待ち望んでいるとは都会に住む者でも言えない言葉だ。
6年ほど前に能登半島を一周する旅をした。輪島の朝市、白米千枚田、禄鋼崎の白亜の灯台、珠洲市海岸の見附島(軍艦島)、奥能登の里山風景など震災被害のあった観光地を想い出す。まだ余震が続いているようだが早期に復興することを願ってやまない。(2024.1.6) |